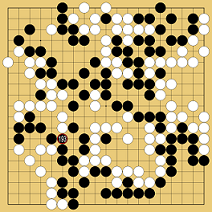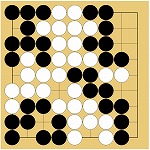2021メール碁会通信(38)
2021. 9.25
五代才助と囲碁十訣 清永 忠
先週号で触れた「囲碁十訣」に関連することについて少々記してみよう。
五代友厚(1836~1885)は、15~16歳のころ藩主・島津斉彬から「才助」で通称され、西郷隆盛、大久保利通と並び、「薩摩の三才」と呼ばれ、大久保利通とは親交が厚かった。
大阪では商工業発展に大きな足跡を残し、関西では恩人として慕われ、確かな信用と幅広い人脈を築いた。明治2年、自らが英和辞書を薩摩藩学生の名で出版、「薩摩辞書」を完売する功績も遺した。五代と大久保は囲碁仲間でもあった。大阪会議を実現し、五代と別れると大久保はその心境を漢詩に賦している。題は「明治8年冬日、碁を打ち偶(たまたま)作る 兼(あわ)せて松陰君(五代)に送る」。2人は夜の更けるのも忘れて碁を打ち、その音が、雪が閑かな窓を叩く音と混じり合っている。対局の中に、素晴らしい妙味のあることは2人しかわからない。2人には勝敗を競う心は毛頭ないという意である。
五代は中国の古典「囲碁十訣」の極意を大久保に伝授し、大久保政権の富国強兵、殖産興業政策を支えたのは五代だと思われる。五代と大久保の共通点は、死後借金を残すほど私利私欲がなかったことと、神として祀られることもなかったということである。
囲碁十訣は、 囲碁の心構えを説いた中国古より伝わる10の格言で、唐代の名手王積薪の作と伝えられるが、北宋時代の作とする説もある。宋代の詰碁集『玄玄碁経』の序の部に王積薪作として収められ、その後の多くの棋書にも収録された。南唐の高官から北宋の太祖に仕えて碁の相手を務めた、潘慎修が太祖に献上した書物『棋説』の中で、「十要」として記した碁の原理が囲碁十訣であるとも言われる。
十訣と大意
1・ 不得貪勝(貪って勝とうとしてはいけない)
2・ 入界宜緩(敵の勢力圏では緩やかにすべし)
3・ 攻彼顧我(攻める時には自分を顧みよ)
4・ 棄子争先(石を捨てて先手を取れ)
5・ 捨小就大(小を捨て大を取れ)
6・ 逢危須棄(危険になれば捨てるべし)
7・ 慎勿軽速(足早になりすぎるのは慎め)
8・ 動須相応(敵の動きに応じるべし)
9・ 彼強自保(敵が強ければ自らを安全にすべし)
10・勢孤取和(孤立している時には穏やかにすべし)
(注)1.の「不得貪勝」を日本で「貪れば勝ちを得ず」と訳して、「貪不得勝」と誤記する場合
がある。
日本メール碁会日本メール碁会日本メール碁会日本メール碁会日本メール碁会